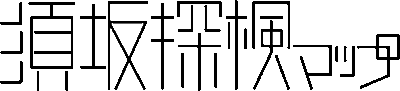須坂市街より国道406号を仁礼、豊丘方面に行く途中、左側に小さな石でできた「元標」があります。
これは「三原道<ミハラドウ>の元標」と呼ばれ、「中町の辻」より伸びた大笹街道である仁礼道から北上州へ向かう「三原道」が分岐する地点を示し、昔の通行者の「道しるべ」に使われたものです。
正面に「右仁礼道、左灰野道」と彫られています。
また元標の左側には「寛政八年」右側には「油仲間連中」と刻まれていることから今から200年前にこの辺りの油屋仲間が建てたことがわかります。
北上州へ向かう三原道は「灰野道<ハイノミチ>」と呼ばれていたのですね。
かつて須坂には油商人が沢山いました。そもそも須坂は明治時代に製糸業が発達する以前、裏川用水を利用して水車を回し、油絞りや穀商が早くから発達していたのです。
裏川用水とは・・・
他の地域の用水は町の真ん中を流れていますが、須坂の用水は屋敷の中を流れているのです。その為に水車をかけるのが容易で産業に利用しやすのです。
明治時代以降、須坂では裏川用水にかけた水車を利用して器械製糸が発達したのです。
「三原道」は灰野を通り抜け、干俣<タマナ>に通じる山道ですが、その交通手段として牛が使われていたようです。
そのために昔から灰野村では和牛の飼育、生産が盛んで、後に洋牛導入による品種改良が行われ、県下に名声をひろめた「灰野牛」生産へとつながっていくのです。