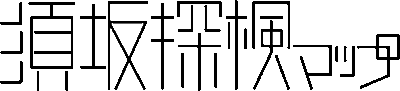長野県須坂市は「信州須坂 蔵の町」として蔵の並ぶ町並みを主な観光材料として全国にPRしています。
そもそも蔵づくりとは・・・。
色々な資料をみると「大壁作り」や「蔵作り」、「土蔵作り」などを見かけますが、一番の違いは火災に対する強さの違いのようです。
「蔵作り、土蔵作り」は同時代の一般の家に比べて、壁が土壁でできているため「耐火」に優れています。しかし壁の厚みや柱や木材が外に出ているために火力によっては燃えてしまうのです。
「大壁作り」は柱などが内からも外からも出ないように壁面内に納め、土壁の厚さも「蔵作り」よりも厚いので「防火」に優れて燃えないのです。
大壁作りの壁には「乳鍵<チチカギ>」が付いています。
乳鍵とは、数年おきに行う漆喰の補修の際に立てる足場に使う柱を結びつけるためのものなのです。
壁のメンテナンスのことまで考えた設計なのです。
また、須坂の蔵のまちは「まゆ蔵のまち」ということです。
明治時代から昭和の初期まで、蚕がつくる繭から生糸を紡ぐ「製糸業」が盛んに行われました。
1年間工場を稼働するために、繭を保存しておかなければなりません。そこで、須坂では繭蔵が多く作られました。
繭蔵の目的は「繭の品質が落ちないように保存する」ですから、土蔵ほど土壁が厚くなく、窓にも土扉がついていません。
それどころか、窓は大きく設置され、通気性と荷の出し入れがしやすく作られているのです。
僕は、こうして須坂の郷土史などを調べる前までは、恥ずかしながら茶色い壁は「土蔵」白い壁は「蔵」なのだと思っていました。
しかし「白い壁」は「茶色い壁」に漆喰<シックイ>という石灰に麻などの繊維や川砂を混ぜてペースト状にしたものを塗った壁なのです。
僕の思い込みは、全くの誤解でした。
漆喰の特徴も「防火」に優れていることです。
また、雨や風にも強く、季節によって湿気を吸収して調節もしてくれるので、建物が劣化しずらくカビもつきにくいのです。
ではどうして全ての蔵に漆喰が塗っていないのでしょうか?
それは一代で全てを完成させるのではなく、仕事を残すことで次世代にも頑張ってもらい家の繁栄を継続させる
という粋な考えがあったようです。
しかし、その後の須坂の製糸業の衰退や経済の変化によって「茶色の壁」の蔵が残ったのです。
現在、須坂市内では漆喰を塗ってある壁が剥がれてしまった蔵を沢山見かけます。
漆喰の内側の土壁は粘土の為に、むき出しだと雨や風に弱く、このままではどんどん風化してしまいます。
壁内部がしっかりしている内に補修をしてあげたいものですね。
少なくても「蔵の並ぶ町並み」を売りにしている須坂市なのだからどうにかできないものでしょうか・・・。
考えていきたいです。